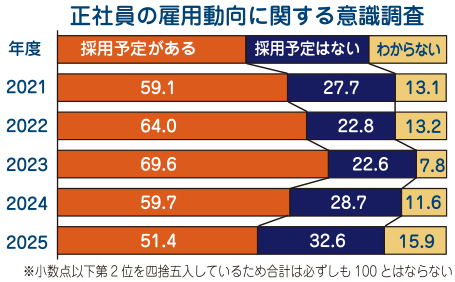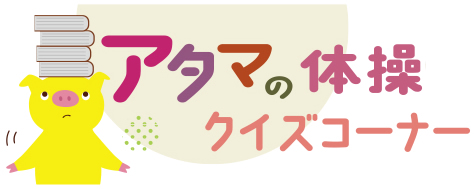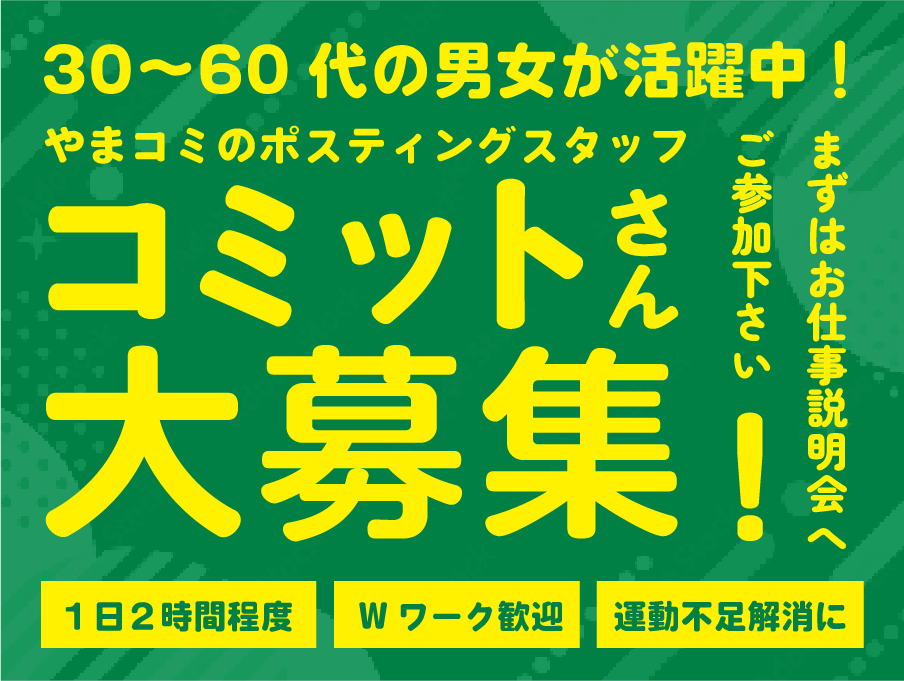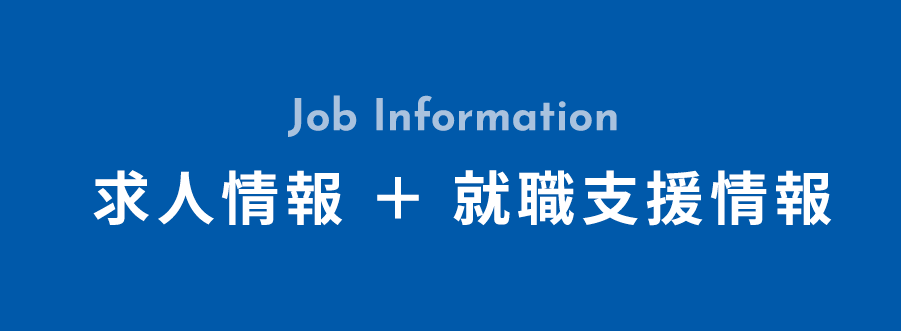-
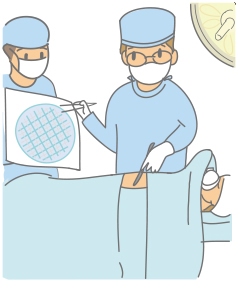 鼠径ヘルニア(下)山形済生病院から 記事を読む 2025.06.25
鼠径ヘルニア(下)山形済生病院から 記事を読む 2025.06.25 -
 背部錯感覚症どうしました?内科 記事を読む 2025.06.25
背部錯感覚症どうしました?内科 記事を読む 2025.06.25 -
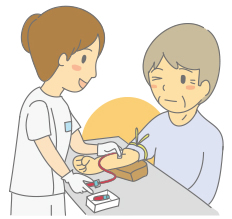 前立腺がんの診断泌尿器講座 記事を読む 2025.06.25
前立腺がんの診断泌尿器講座 記事を読む 2025.06.25
-
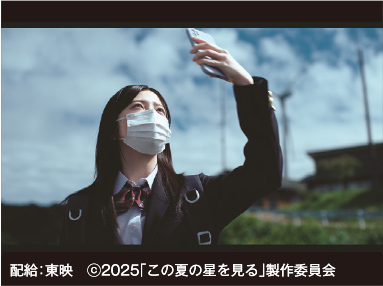 〈荒井幸博のシネマつれづれ〉この夏の星を見る荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.26
〈荒井幸博のシネマつれづれ〉この夏の星を見る荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.26 -
 《鰻の成瀬》安さとうまさで全国を席巻中せっかく行くならこんな店 記事を読む 2025.06.12
《鰻の成瀬》安さとうまさで全国を席巻中せっかく行くならこんな店 記事を読む 2025.06.12 -
 〈荒井幸博のシネマつれづれ〉ルノワール 6月20日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.11
〈荒井幸博のシネマつれづれ〉ルノワール 6月20日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.11
-
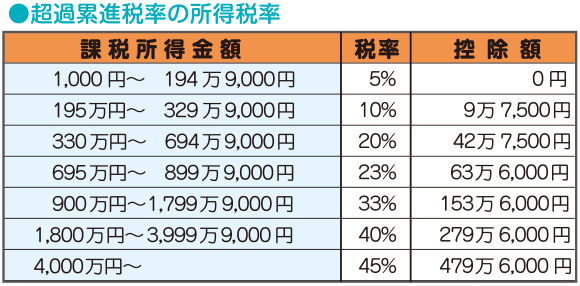 税金の基礎知識/(13)所得税と住民税、異なる税率税金の基礎知識 記事を読む 2025.06.26
税金の基礎知識/(13)所得税と住民税、異なる税率税金の基礎知識 記事を読む 2025.06.26 -
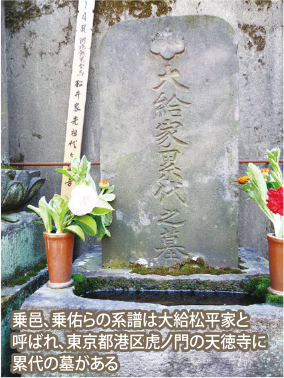 それからの山形藩/第17回 左遷人事で松平氏が入部それからの山形藩 記事を読む 2025.06.25
それからの山形藩/第17回 左遷人事で松平氏が入部それからの山形藩 記事を読む 2025.06.25 -
 《セピア色の風景帖》第190回 もと紀(山形市)セピア色の風景帖 記事を読む 2025.06.11
《セピア色の風景帖》第190回 もと紀(山形市)セピア色の風景帖 記事を読む 2025.06.11

BOOKSセールスランキング
協力:戸田書店 山形店
- 一般書籍
- コミック
- 文庫
独断と偏見
集英社
高宮麻綾の引継書
文藝春秋
パズルと天気
PHP研究所
カフネ
講談社
クロエとオオエ
講談社
ブルーロック 34
講談社
転生したらスライムだった件 29
講談社
鬼の花嫁 7
スターツ出版
魔入りました!入間くん 43
秋田書店
舞妓さんちのまかないさん 30
小学館
薬屋のひとりごと 16
主婦の友社
青瓜不動 三島屋変調百物語九之続
KADOKAWA
関ケ原仁義 中
双葉社
国宝(上 青春篇、下 花道篇)
朝日新聞出版
営繕かるかや怪異譚 3
KADOKAWA
2025年06月26日 現在
やまコミについて