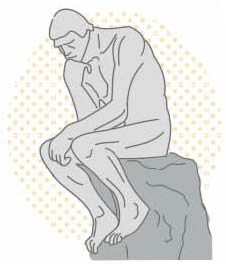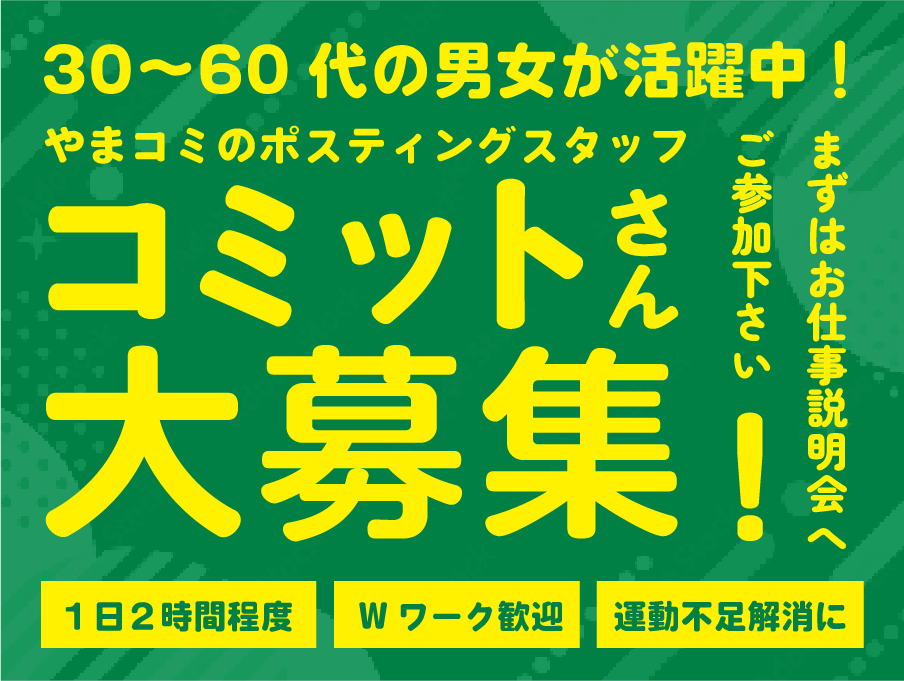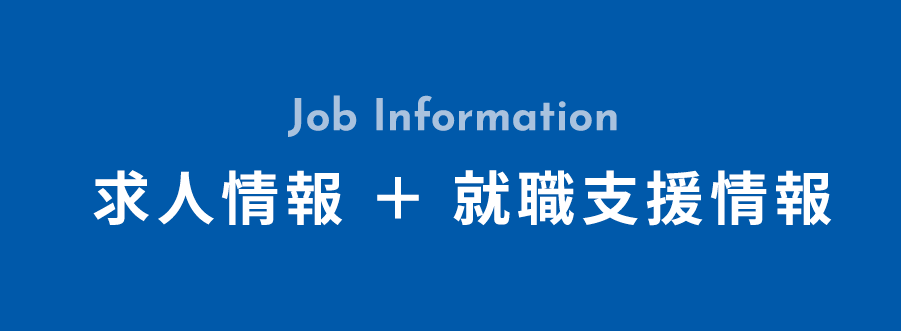下肢救済治療
糖尿病などが原因で足(下肢)の血流が悪くなり、やむなく切断を迫られる人は少なくありません。今回はそんな不幸な事態を回避するための「下肢救済治療」のお話です。
年間1万人が下肢切断
どんな時に下肢を失う可能性があるかというと、①下肢の血行障害②感染症③血行障害+感染症によって生じる足の壊疽(えそ・組織が深いところまで死んでしまった状態)などの場合です。
病態に応じた適切な治療が施されない場合には、下肢の大切断(太ももやふくらはぎでの切断)が必要になります。
国内で下肢切断を余儀なくされる人は年間1万人にのぼるとされます。

バイパス手術も
下肢救済治療は①血流の改善②適切な創傷(そうしょう)の管理③全人的サポートの3つの柱で構成されます。血行障害が原因の場合は、血流改善による足部への栄養や酸素の供給が必須です。その手段としてはカテーテルによる血管拡張や外科的に代用血管を移植するバイパス手術があります。
創傷管理では徹底した洗浄による感染のコントロールと、適切な外用剤などの使用による創傷環境の改善が重要です。
社会的支援が重要
血流や創傷の管理だけでは「歩み続けるいのち」を守ることはできません。下肢救済治療は時間がかかることが多い治療です。適切なリハビリテーションや栄養管理など身体的なサポートに加え、メンタルケアや退院後の生活不安に対する社会的支援が重要です。
多角的視点から患者さんの治療にあたるためには多職種の医療従事者が協働で治療に参画することが必要です。
足も大切な臓器です!
下肢を切断すると生活の質(QOL)に影響が出るばかりか、その後の死亡率も高まります。今回の拙コラムをお読みいただき、「足も大切な臓器」という意識を持っていただければ幸いです。

山形済生病院 心臓血管外科診療部長
外山 洋孝(そとだ ようこう)
1997年山形大学医学部卒業、医学博士、日本外科学会〔専門医、指導医〕、三学会構成心臓血管外科専門医認定機構〔心臓血管外科専門医、修練指導医〕、日本脈管学会〔専門医、指導医〕。