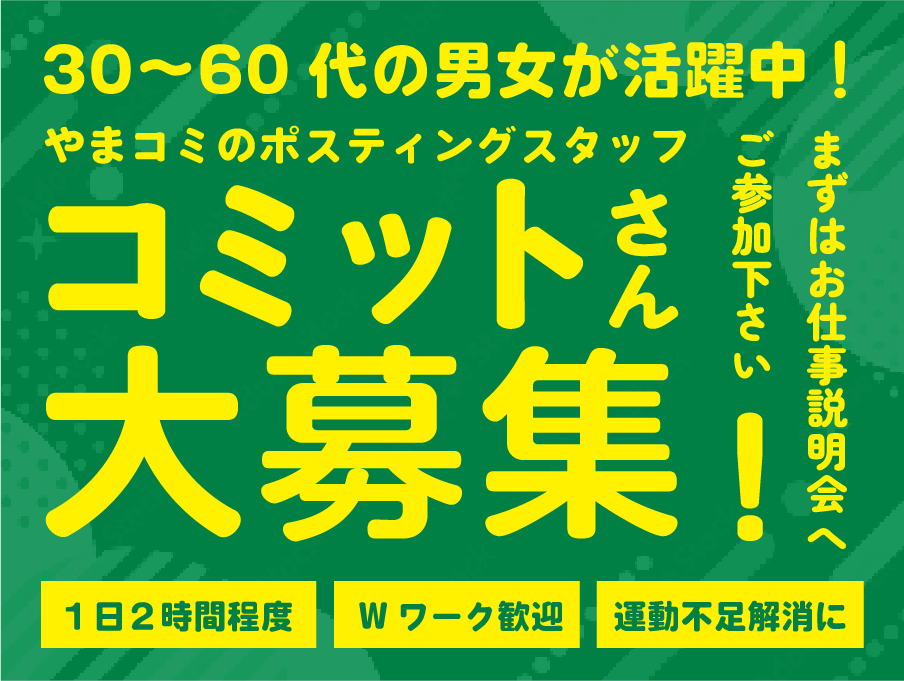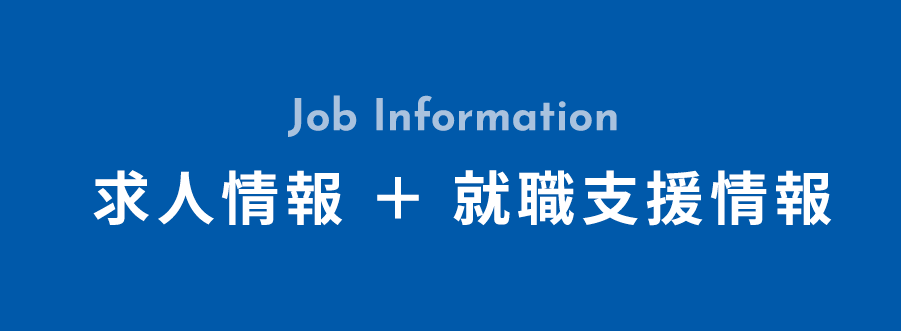セピア色の風景帖
《セピア色の風景帖》第193回 不忘窯跡(上山市)
昭和40年代末、戦後に帰還者が入植した上山市の蔵王開拓村で1人の陶芸家が築窯した。窯主は陶芸界の巨匠、加藤唐九郎のもとで修業を積んだ県内出身者であった。

築窯には耐火煉瓦をはじめとする膨大な材料を必要とするため、瀬戸の廃窯を解体し、トラックで片道700キロあまりの道を十数度も往復をして運んだという。
窯は、蔵王の古称である〝わすれずの山〟から「不忘窯」の名を与えられ、煙を上げることになった。
当時はオイルショックのさなか。また豪雪地帯というハンディを背負いながら、窯を採算に乗せるのは艱難辛苦を伴ったことであろう。
それでもこの地のもたらす作風を大事にし、必死の営業やホテル古窯の支援などもあり、個展を開くたびに大きな反響と成功を収めたようだ。一般品も地元の支持を集め、代表作「笑顔の湯のみ」は多くの人の手元に行き渡っていた。
ただ、現在は不忘窯から煙が上ることはない。平成に入り、窯主は活躍の場を海外に求めて渡米したと聞いているが、跡地となって久しく、廃窯の理由は明らかになっていない。(F)