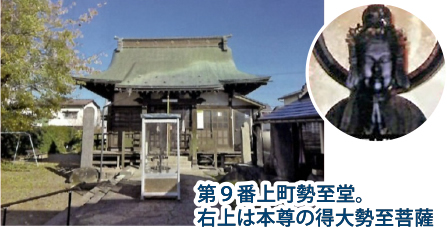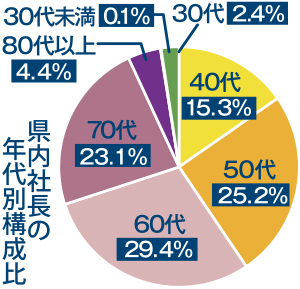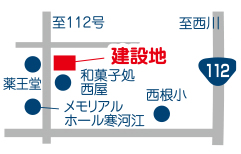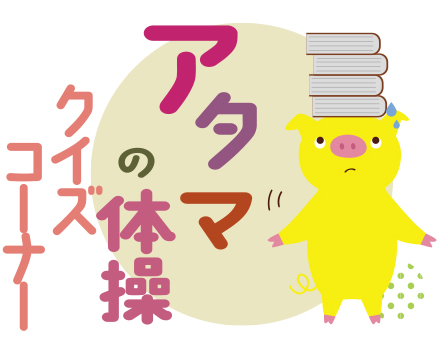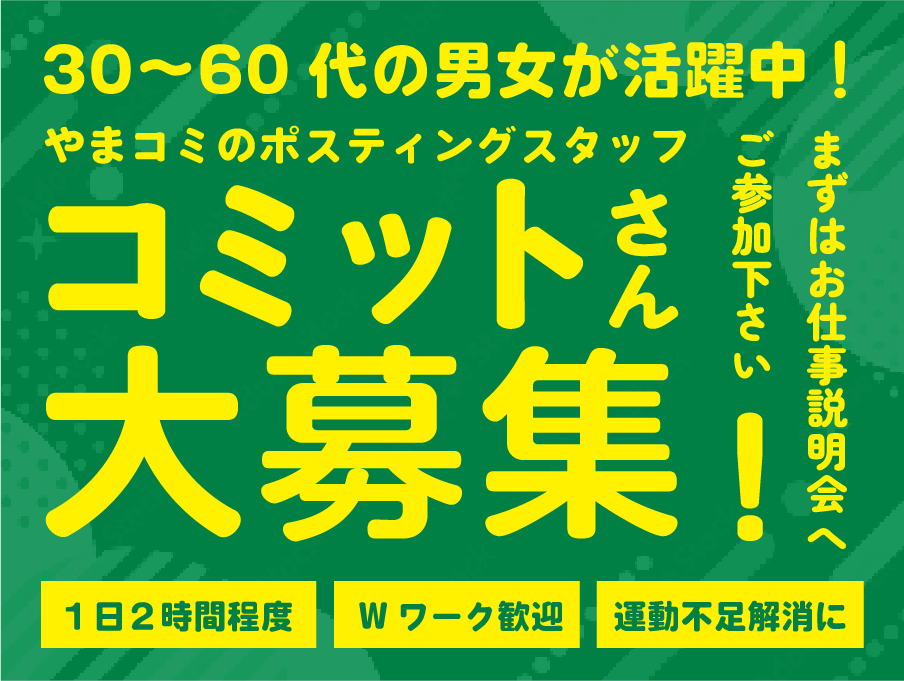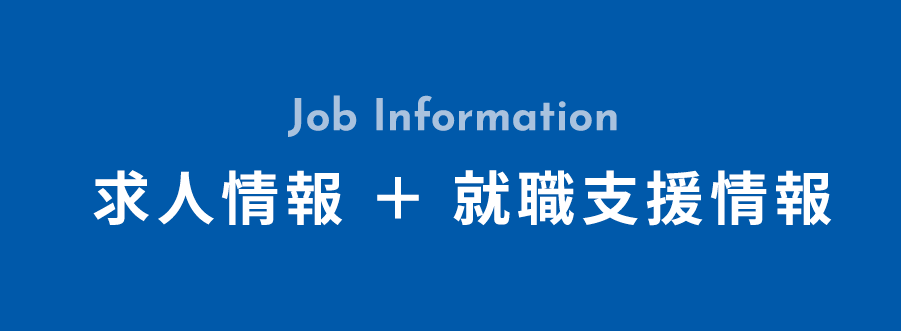-
 片頭痛(上)Let's know 脳! 記事を読む 2025.05.07
片頭痛(上)Let's know 脳! 記事を読む 2025.05.07 -
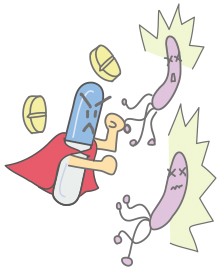 ピロリ菌検査内科あれこれ 記事を読む 2025.05.07
ピロリ菌検査内科あれこれ 記事を読む 2025.05.07 -
 更年期(5)真理子先生の女性のミカタ 記事を読む 2025.05.07
更年期(5)真理子先生の女性のミカタ 記事を読む 2025.05.07
-
 〈荒井幸博のシネマつれづれ〉サブスタンス 5月16日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.05.08
〈荒井幸博のシネマつれづれ〉サブスタンス 5月16日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.05.08 -
 〈荒井幸博のシネマつれづれ〉花まんま 4月25日(金) 全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.23
〈荒井幸博のシネマつれづれ〉花まんま 4月25日(金) 全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.23 -
 〈荒井幸博のシネマつれづれ〉大好き~奈緒ちゃんとお母さんの50年~荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.10
〈荒井幸博のシネマつれづれ〉大好き~奈緒ちゃんとお母さんの50年~荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.10
-
 コツを知ったら毎日楽しい 家事ラク講座《33》お料理編 春野菜でヘルシーレシピ家事ラク講座 記事を読む 2025.05.08
コツを知ったら毎日楽しい 家事ラク講座《33》お料理編 春野菜でヘルシーレシピ家事ラク講座 記事を読む 2025.05.08 -
 相続の基礎知識/(69)iDeCoについて相続の基礎知識 記事を読む 2025.05.08
相続の基礎知識/(69)iDeCoについて相続の基礎知識 記事を読む 2025.05.08 -
 それからの山形藩/第14回 堀田氏が大坂城代、老中もそれからの山形藩 記事を読む 2025.05.08
それからの山形藩/第14回 堀田氏が大坂城代、老中もそれからの山形藩 記事を読む 2025.05.08

BOOKSセールスランキング
協力:戸田書店 山形店
- 一般書籍
- コミック
- 文庫
カフネ
講談社
歴史のダイヤグラム<3号車>
朝日新聞出版
高宮麻綾の引継書
文藝春秋
田んぼのまん中のポツンと神社
飛鳥新社
知りたいこと図鑑
KADOKAWA
アオアシ 39
小学館
ハニーレモンソーダ 28
集英社
アオのハコ 20
集英社
ドカ食いダイスキ!もちづきさん 2
白泉社
薬屋のひとりごと 15
スクウェア・エニックス
マスカレード・ゲーム
集英社
ほどなく、お別れです
小学館
#真相をお話しします
新潮社
棘の家
KADOKAWA
チンギス紀 七 虎落
集英社
2025年05月08日 現在
やまコミについて